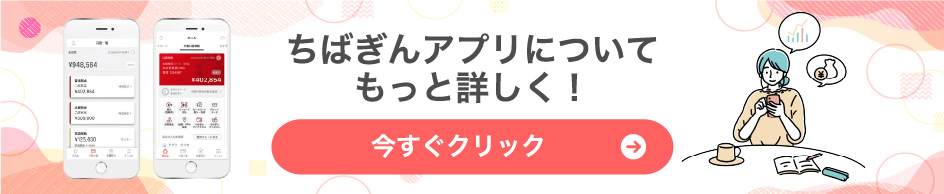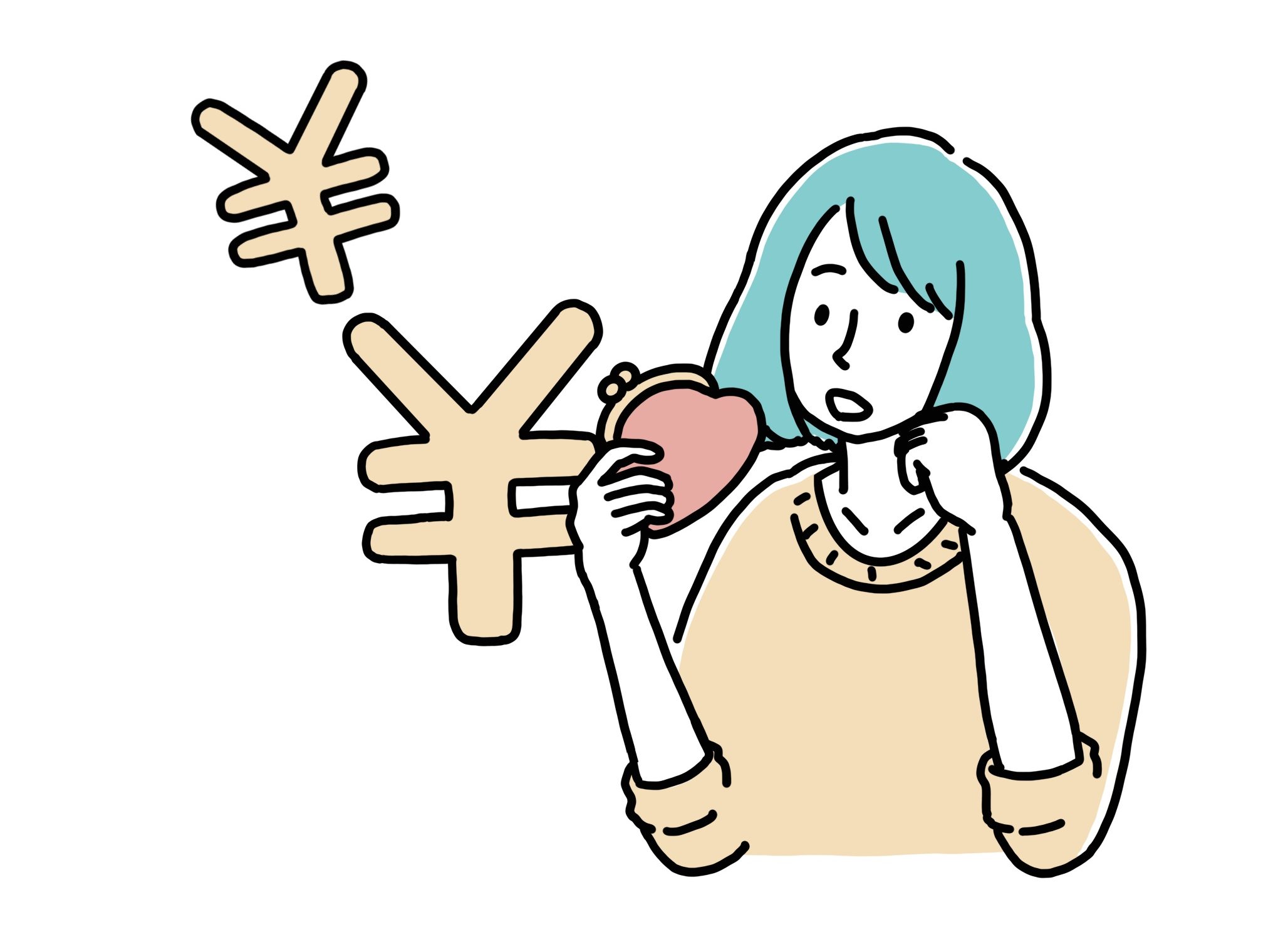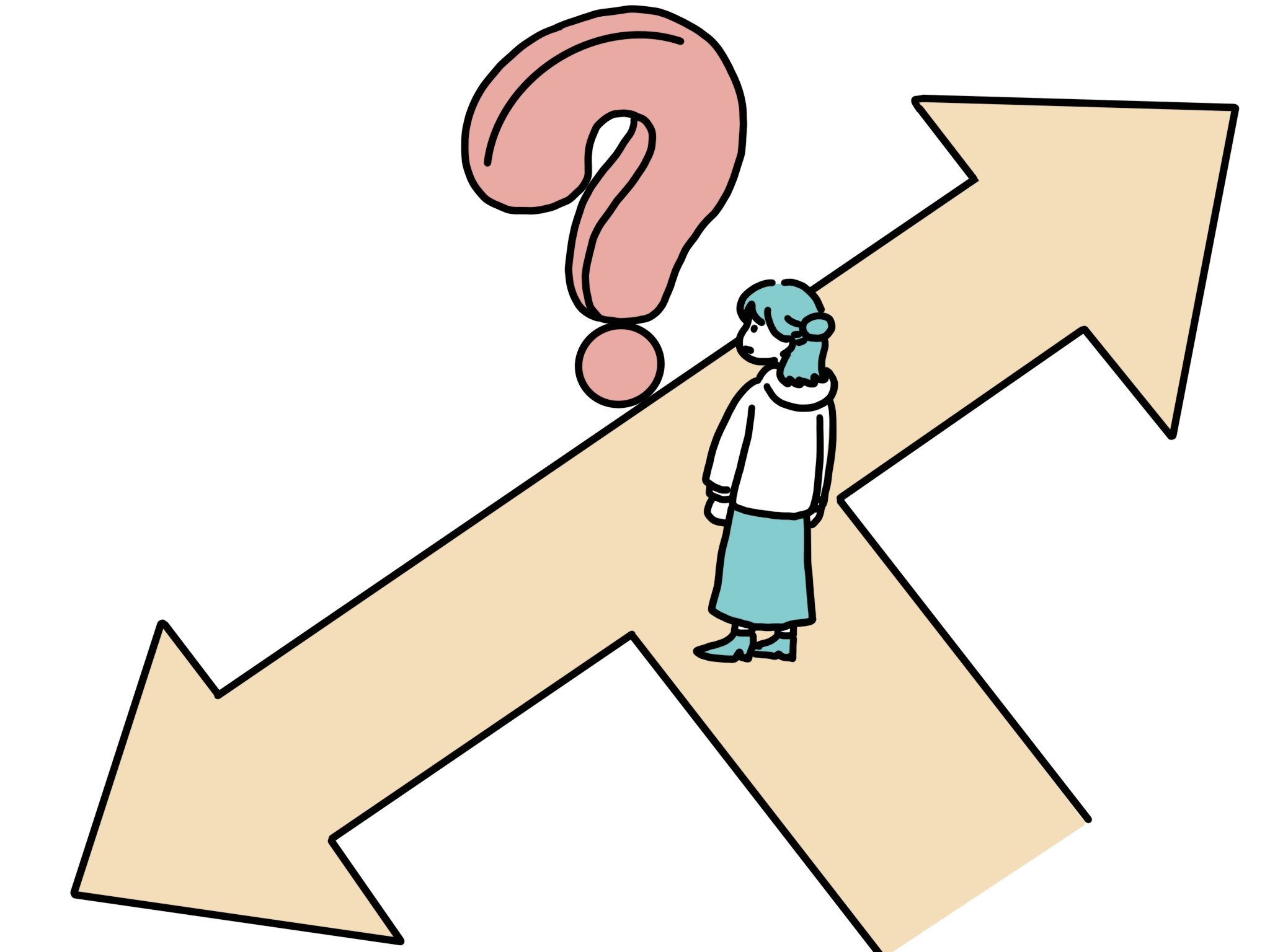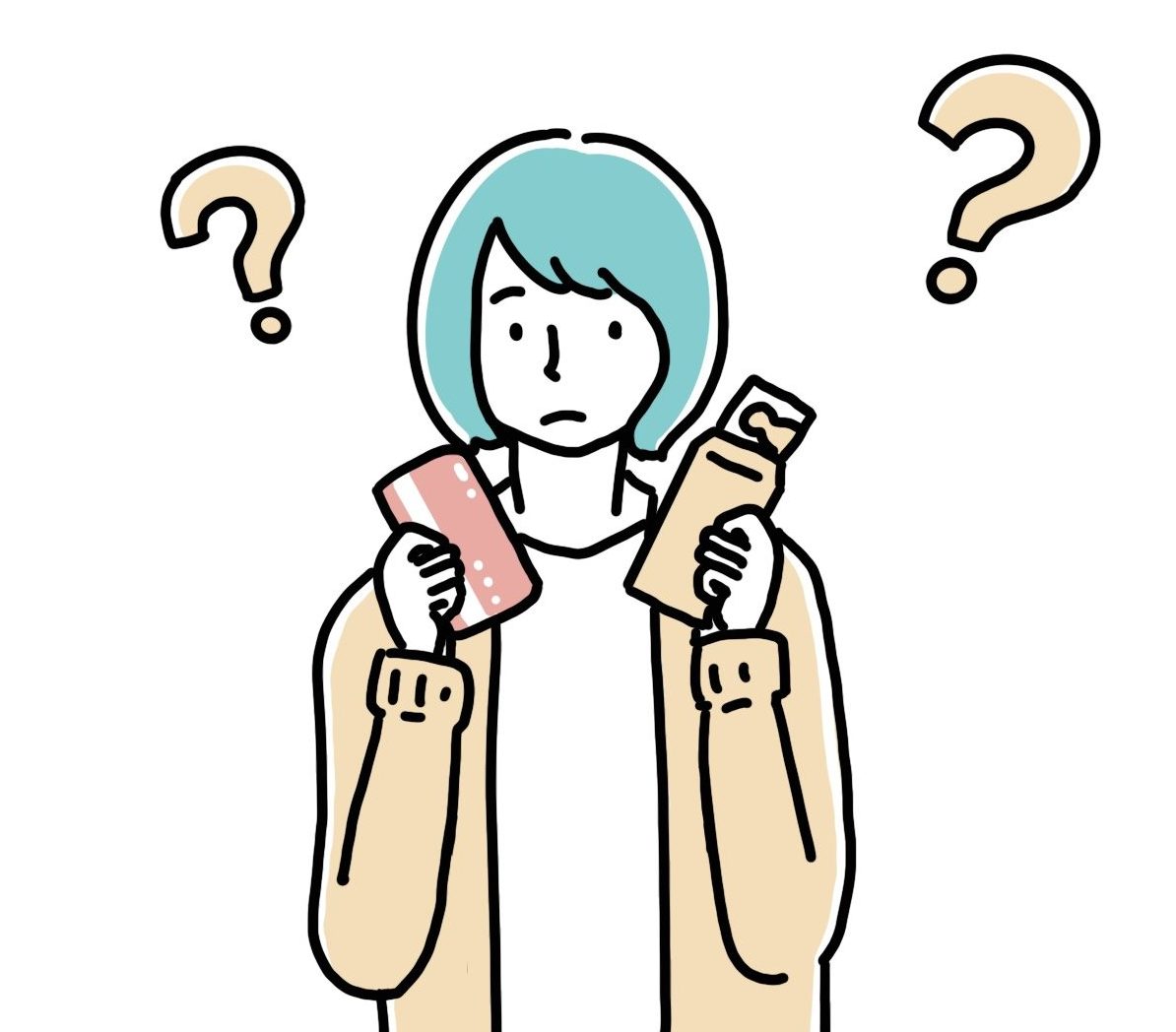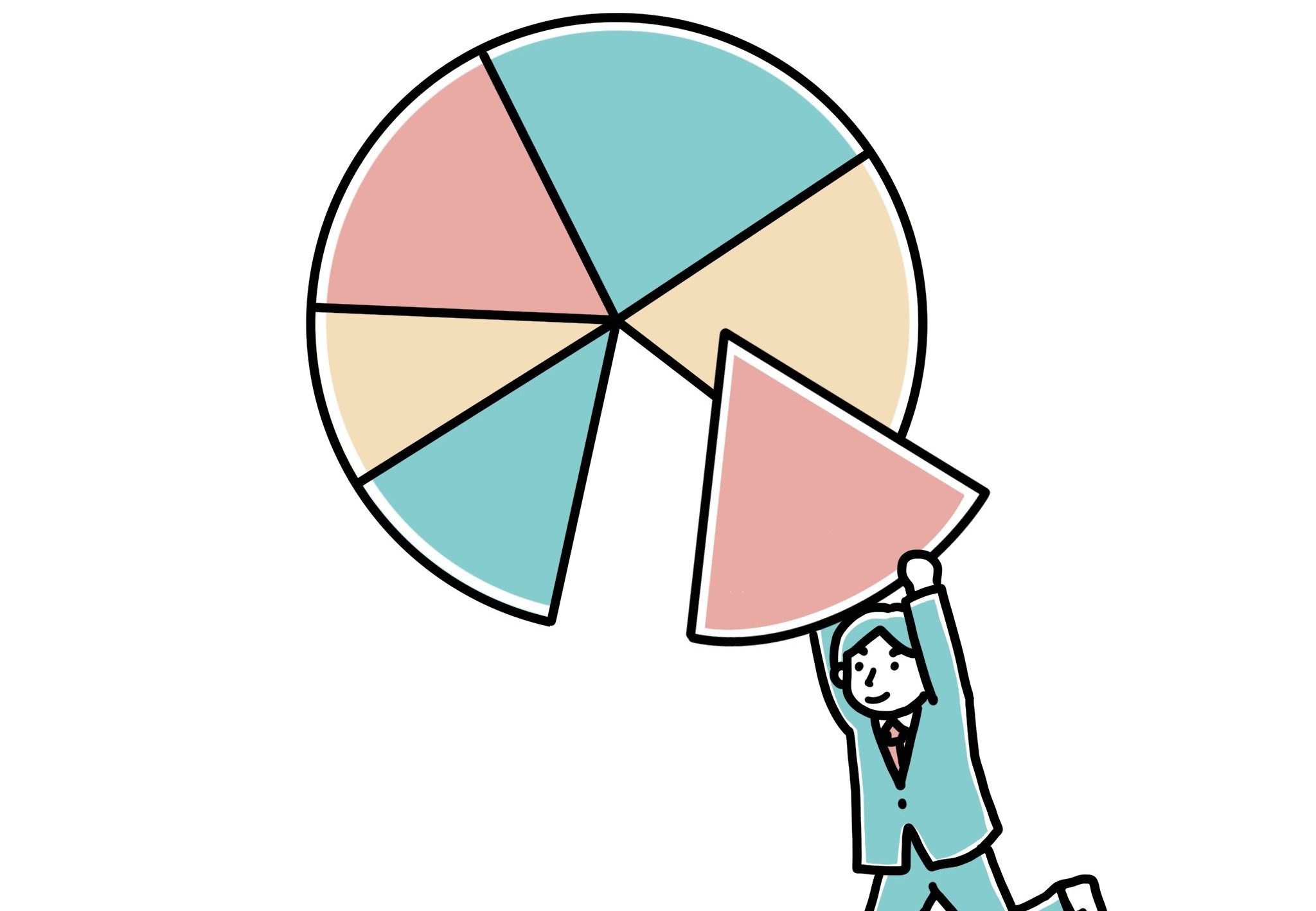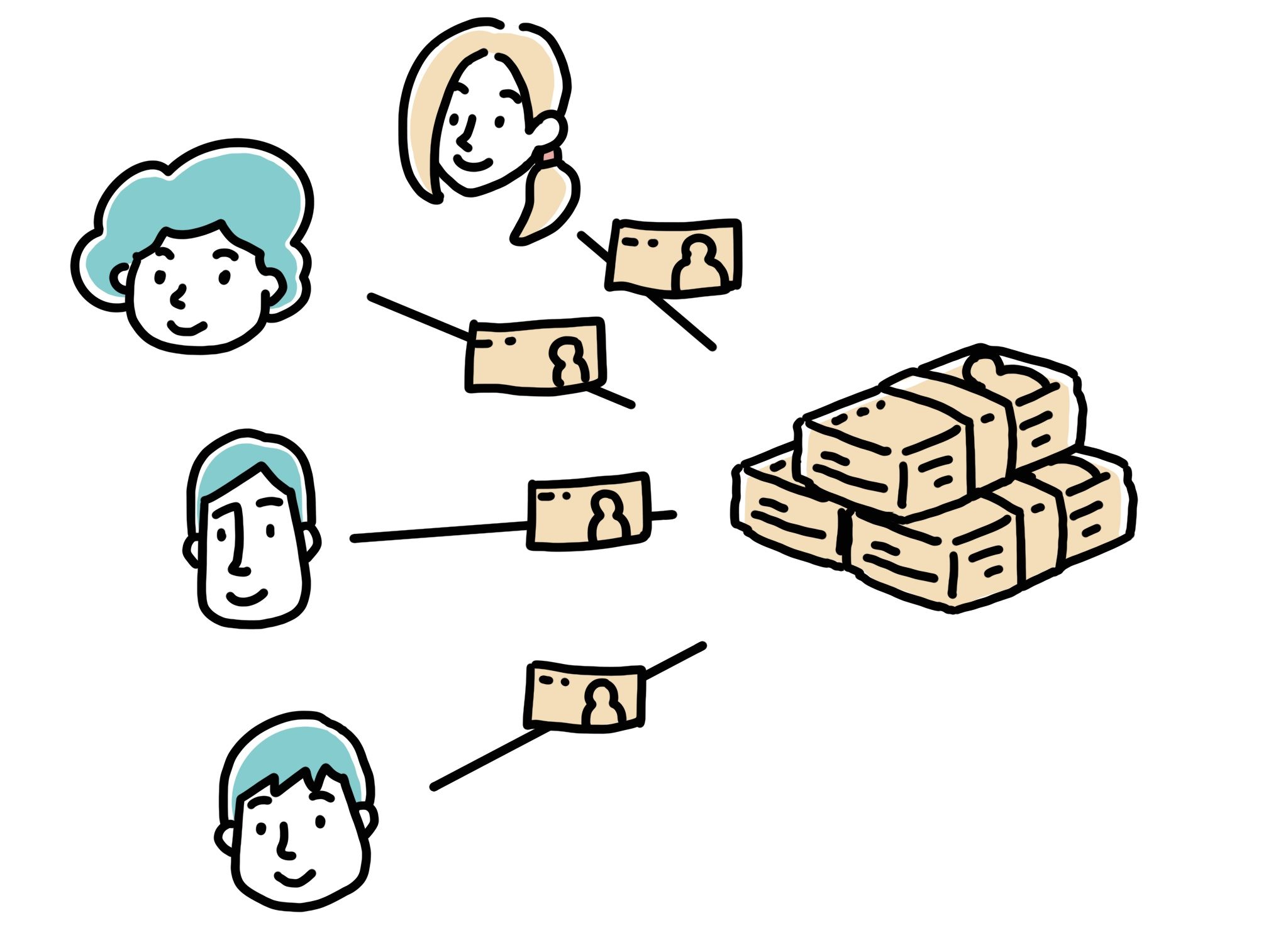定期預金とは?メリット・デメリットや普通預金との違い・運用方法を解説
定期預金は、期間を決めて金融機関にお金を預ける金融商品のことで、普通預金と比べて金利が高いのが特徴です。
本記事では、定期預金の仕組みや特徴、メリット・デメリット、普通預金との違い、そして効果的な運用方法まで詳しく解説します。資産形成に役立つ知識を身につけましょう。

公開日:
更新日:2025.07.01
目次
定期預金とは?
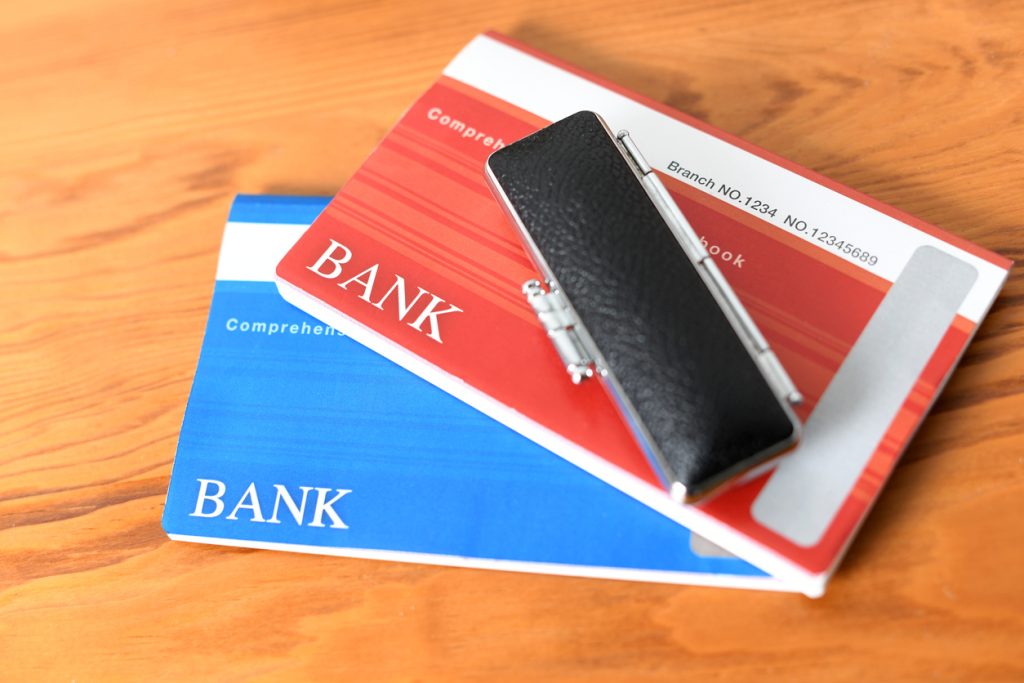
定期預金とは、あらかじめ決めた期間、お金を金融機関に預け入れる金融商品です。
そもそも預金とは、お金を銀行などの金融機関に預けることで、定期預金はその中でも一定期間預け入れることを約束するタイプの預金を指します。普通預金と異なり、原則として満期日までお金を引き出すことができない代わりに、より高い金利が設定されるのが特徴で、資産形成の選択肢の一つとして広く利用されています。
また、定期預金には一般定期預金(スーパー定期 等)、大口定期預金、積立式定期預金などの種類があり、それぞれ特徴や向いている目的が異なります。
以下では、定期預金の仕組みや特徴、種類、普通預金との違いについて詳しく解説していきます。
定期預金の仕組みと特徴
定期預金の主な特徴は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 預入期間の設定 | ・金融機関により上限は異なる ・一般的な期間:1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、5年 |
| 金利の種類と計算方法 | ・固定金利型(預入時の金利が満期まで適用)と変動金利型(一定期間ごとに金利が変更)がある ・計算方法は単利計算と複利計算の2種類がある |
| 払戻しの制限 | ・満期まで原則として払戻し不可 ・手続きを踏むことで中途解約は可能(ただし金利が低下する) |
| 預入方式 | ・定型方式:一定期間で預け入れ ・満期日指定方式:満期日を自由に設定可能 |
| 満期後の取扱い | ・元利自動継続(元金と利息を合わせて継続) ・元金自動継続(元金のみ継続し、利息は普通預金へ) ・自動解約(元金と利息を普通預金へ) |
| 預金保険制度 | ・元本1,000万円までと破綻日までの利息を保護 ・普通預金等と合算で保護 |
なお、これらの内容は各金融機関によって詳細が異なる場合がありますので、実際に定期預金を開設する際には、金融機関の商品説明をよく確認することが大切です。たとえば、預入期間の選択肢や金利の水準、中途解約時の取扱いなどは金融機関ごとに差があります。
定期預金の主な種類
定期預金には主に3つの種類があり、それぞれ特徴や向いている目的が異なります。自分の資産形成の目的や状況に合わせて最適な種類を選ぶことが重要です。
| 種類 | 特徴 | 主な目的 |
| 一般定期預金(スーパー定期 等) | • 最もスタンダードな定期預金 • 一括で預け入れ • 固定金利型 | • 一般的な資産形成 • まとまった資金の運用 • 将来に備える資金の確保 |
| 大口定期預金 | • 大口資金専用の定期預金 • より有利な金利設定 • 固定金利型と変動金利型がある | • 退職金の運用 • 不動産売却資金の運用 • 法人の余剰資金の運用 |
| 積立式定期預金 | • 毎月一定額を自動振替で積立 • コツコツ貯める形式 • 普通預金口座からの自動振替 | • 住宅購入の頭金準備 • 教育資金の準備 • 自動車購入資金の準備 |
一般定期預金(スーパー定期 等)
一般定期預金(スーパー定期 等)は、最も一般的な定期預金の形態です。まとまったお金を一度に預け入れ、一定期間後に元金と利息を受け取る仕組みとなっています。
最低預入金額は金融機関によって異なりますが、多くの場合1万円から預け入れ可能です。預入期間は1か月から10年程度まで選べる金融機関が多く、期間が長いほど金利が高く設定される傾向があります。
金利は預入時に決定され、満期まで変わらない固定金利が一般的です。安全性の高い金融商品として人気があります。
一般定期預金(スーパー定期 等)は、退職金や賞与などのまとまった資金を安全に運用したい方や、将来の大きな出費に備えてお金を確保しておきたい方に向いているといえるでしょう。比較的少額から始められるため、資産運用の初心者にも適しています。
大口定期預金
大口定期預金は、一般定期預金(スーパー定期 等)と基本的な仕組みは同じですが、預入金額が1,000万円以上と高額な点が特徴です。まとまった資金を効率的に運用したい方に適しています。
最低預入金額は1,000万円となっており、この金額以上の預け入れが必要です。預入期間は一般定期預金と同様に1か月から10年程度まで選べることが多いです。
金利は一般的に一般定期預金(スーパー定期 等)よりも高く設定されていることが多く、運用効率を高めたい方にとって魅力的といえます。ただし、1,000万円とその利息を超える部分については、預金保険制度の保護対象外となる点には注意が必要です。
大口定期預金は、不動産売却代金や相続資金、企業の余剰資金など、高額な資金を持つ方や法人に向いています。安全性を重視しつつ、できるだけ高い金利で運用したい場合に検討する価値があるでしょう。
積立式定期預金
積立式定期預金は、毎月一定額を自動的に積み立てていく形式の定期預金です。少額から始められ、コツコツと資産を形成していきたい方に適しています。
最低預入金額は金融機関によって異なりますが、月々500円や1,000円といった少額から始められるところが多いです。預入期間もさまざまで、目標日を指定できるタイプや、期間を定めずに継続して積み立てるタイプなどがあります。
金利は一般定期預金と同様に預入時の金利が適用されることが多いですが、積立のタイミングによって適用金利が変わる場合もあります。自動的に毎月積み立てられるため、貯蓄の習慣化につながるというメリットも。
積立式定期預金は、教育資金や結婚資金、旅行資金など将来のために計画的な貯蓄をしたい方や、貯蓄が苦手な方に向いています。無理なく継続できる金額から始められるため、長期的な資産形成の第一歩としても最適です。
普通預金との違いとは
普通預金と定期預金は、いずれも銀行などの金融機関で利用できる預金商品ですが、金利やリスクに違いがあります。両者の特徴を正しく理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。
| 比較項目 | 普通預金 | 定期預金 |
| 出し入れの自由度 | • いつでも自由に出し入れ可能 • ATMや窓口で随時引出し可 • 残高の範囲内で制限なし | • 預入期間が固定 • 原則として満期まで引出し不可 • 中途解約には手続きが必要 |
| 金利 | • 低め • 残高にかかわらず一定 | • 普通預金より高め • 預入期間や金額により変動 • 期間が長いほど高金利 |
| 主な使用目的 | • 給与や年金の受取 • 公共料金等の支払い • 日常的な支出の管理 | • まとまった資金の運用 • 将来に備えた資金の確保 • 計画的な資産形成 |
| 付帯できる機能の例 | • 自動引き落とし • クレジットカード決済 • 給与振込 • 各種料金支払い | • 自動継続機能 • 満期時の選択機能(元利継続/元金継続/解約) |
| 向いている資金の性質 | • 日常的な支出に必要な資金 • 急な出費に備えた資金 | • すぐには使用しない資金 • 使用時期が決まっている資金 |
| リスク | • 金利が極めて低い • インフレによる実質価値の低下 | • 中途解約時の金利低下 • インフレリスク • 期間拘束のリスク |
普通預金は、日常生活で頻繁に使うお金の管理に適しています。給与の受け取りや公共料金の支払い、日々のお買い物など、頻繁に入出金が発生する資金に向いています。一方で金利が低いため、長期間預けていても大きく増えることはありません。
一方で定期預金は、まとまった資金を長期間預け入れるのに適しています。普通預金よりも高い金利が設定されていることが多いため、より効率的に資産を増やすことができます。ただし、満期前に引き出すと金利が低下するため、すぐに使う予定のないお金を預け入れることが重要です。
両方のメリット・デメリットを理解し、日常的に使用する資金は普通預金で、余裕資金は定期預金で運用するといった使い分けが効果的です。また、緊急時の備えとしての資金は、一部を普通預金に残しておき、残りを定期預金に預けるというバランスも考慮するとよいでしょう。
定期預金のメリット

定期預金には以下のようなメリットがあります。
- 普通預金より高い金利が得られる
- 預金保険制度による元本保証(1,000万円とその利息を超える預金部分は、元本保証の対象外)
- 計画的な資産形成が可能
- 手数料がかからない
これらのメリットにより、定期預金は安全性の高い資産形成手段として多くの人に利用されています。特に、リスクを抑えながら資産を形成したい方や、将来の大きな出費に備えて計画的に貯蓄したい方にとって、定期預金は有効な選択肢となるでしょう。
普通預金より高い金利が得られる
定期預金のメリットの一つは、普通預金と比較して金利が高い点です。これは、定期預金が預入期間を定めて資金を拘束するため、金融機関がその資金を長期的に運用できるからです。
現在の金融環境では、普通預金の金利は0.2%程度と非常に低く設定されていることが多いですが、定期預金は預入期間や金額によって異なるものの、0.25%から0.5%程度の金利が設定されていることが一般的です。一見すると小さな差に思えるかもしれませんが、預入金額が大きくなるほど、あるいは預入期間が長くなるほど、その差は大きくなります。
具体的な例を見てみましょう。100万円を預け入れた場合、普通預金(金利0.2%)では1年間で2,000円(税引前)の利息しか得られませんが、定期預金(金利0.5%)なら5,000円(税引前)の利息が得られます。これは2.5倍の差になり、預ける金額が増えればそれだけ多くの利息がつきます。さらに、大口定期預金や特別金利キャンペーンを利用すれば、より高い金利を得られる可能性もあります。
預入期間による金利の違いも重要なポイントです。一般的に、定期預金は預入期間が長いほど金利が高く設定されています。たとえば、1か月の定期預金より1年の定期預金、1年の定期預金より3年や5年の定期預金のほうが高い金利が適用されることが多いです。長期間使う予定のない資金であれば、長めの預入期間を選ぶことで、より効率的に資産を増やすことができるでしょう。
預金保険制度による元本保証
定期預金は、預金保険制度による元本保証があります。この制度により、万が一金融機関が破綻した場合でも、預金者の資産が一定額まで保護されます。
預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者を保護するための制度です。日本では、預金保険機構がこの制度を運営しています。この制度により、1金融機関ごとに預金者1人あたり1,000万円までの元金とその利息が全額保護されます。対象となる金融機関は銀行や信用金庫、労働金庫などの民間金融機関です。
保護される預金の範囲は、普通預金や当座預金、定期預金などの円預金です。外貨預金や譲渡性預金(CD)、金融債などは保護の対象外となります。また、元本1,000万円を超える部分については、金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされる可能性もあります。
この元本保証の仕組みは、定期預金の大きな安心感につながっています。
安全性の高さを求める投資家にとって、定期預金は基本的な金融商品としての価値があります。リスク資産とのバランスを考えながら、ポートフォリオの一部に組み込むことで、全体のリスクを抑えつつ資産形成を進めることができるでしょう。
計画的な資産形成が可能
定期預金は、計画的な資産形成を実現するための有効なツールです。特に、目的別に資金を管理したい場合や、将来の大きな出費に向けて着実に準備を進めたい場合に役立ちます。
計画的な資産形成を行うには、目的に合わせた定期預金の活用方法があります。たとえば、子どもの教育資金であれば、進学時期に合わせて満期が来るように複数の定期預金を設定することが可能です。中学入学時、高校入学時、大学入学時といった具合に、必要となる時期に合わせて定期預金の満期を設定することで、必要なときに必要な資金を確保できます。
また、積立式定期預金を活用すれば、毎月一定額を自動的に積み立てることができるため、無理なく継続的に資産を増やすことができます。特に、貯蓄の習慣がない方や、つい余ったお金を使ってしまいがちな方には、貯蓄する習慣づけとして有効です。
長期的な資金計画においては、定期預金だけでなく、他の金融商品との組み合わせも検討するとよいでしょう。たとえば、すぐに必要な資金は普通預金に、1〜3年以内に必要な資金は定期預金に、それ以上の長期的な資金はNISAや投資信託などでの運用を検討するといった具合です。
ライフプランに基づいた計画的な資金配分を行うことで、お金に対する不安を減らし、将来の夢や目標に向けて着実に準備を進めることができます。定期預金は、そうした計画的な資産形成を支える基盤となる金融商品です。
手数料がかからない
解約時に手数料がかからない点も、定期預金のメリットの一つです。これは投資信託や株式などの他の金融商品と比較した際の優位性となっています。
投資信託を例にとると、購入時には「購入時手数料」(ノーロード型を除く)、保有期間中には「信託報酬」、解約時には「信託財産留保額」(一部のファンドのみ)などの各種手数料がかかります。株式取引では売買時に「売買委託手数料」などがかかります。これらの手数料は運用成績を圧迫する要因となりえます。
一方、定期預金では預け入れ時、保有期間中、満期解約時のいずれにおいても手数料はかかりません。中途解約をした場合でも、適用金利は低下するものの、別途手数料が発生することはありません。このように、コスト面でもメリットがあるため、少額からでも効率的に資産形成を始めることができます。
定期預金のデメリット

定期預金にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
- 中途解約時の金利低下
- インフレリスクへの脆弱性
- 資産運用としての限界
これらのデメリットを理解したうえで、自分の資産形成の目的や状況に合わせて、定期預金を活用することが重要です。長期的な資産形成を考える際には、定期預金だけでなく、他の金融商品との組み合わせも検討するとよいでしょう。
中途解約時の金利低下
定期預金の主なデメリットの一つに、満期前に引き出す場合(中途解約時)の金利低下があります。これは預金者が当初の契約を破棄するため、金融機関側の運用計画に影響を与えることから、ペナルティとして金利が下がる仕組みです。
中途解約時の金利計算方法は金融機関によって異なりますが、一般的に「中途解約利率」または「期限前解約利率」と呼ばれる、預入時に定められた金利よりも低い金利が適用されます。多くの場合、この中途解約利率は普通預金と同程度、あるいはそれよりもわずかに高い程度の非常に低い金利となります。
具体的な例で考えてみましょう。年利0.2%の5年定期預金に100万円を預け入れた場合、満期まで預け続ければ約1万円の利息が得られます(単利計算、税引前)。しかし、1年後に中途解約した場合、中途解約利率が年0.2%だとすると、利息は2,000円程度に減少。さらに、預け入れからごく短期間で解約する場合には、利息がほとんど付かないケースもあります。
このように、中途解約した場合の金利低下は大きく、定期預金の金利メリットがほとんど失われてしまうことがあります。そのため、定期預金を利用する際には、満期まで引き出す必要がない資金を預け入れることが重要です。将来の資金需要を正確に予測し、必要な時期より少し前に満期が来るように設定するなど、計画的な利用が求められます。
緊急時のために一部の資金を引き出せるように、まとまった資金を複数の定期預金に分散して預け入れるといった工夫も考えられます。また、必要に応じて一部だけを中途解約できる商品を選ぶことも検討するとよいでしょう。
インフレリスクへの脆弱性
定期預金が抱えるデメリットの一つに、インフレリスクへの脆弱性があります。インフレとは物価が上昇する現象で、お金の価値が相対的に目減りすることです。
インフレが進むと、定期預金の利息よりも物価の上昇が大きくなるため、お金の価値が目減りします。たとえば、インフレ率が2%なら、今年100万円で買えたものを来年も買うには102万円必要になります。しかし、定期預金の金利が0.2%なら、1年後に100万2,000円にしか増えません。つまり、同じものを買うには約1万8,000円分足りません。
特に低金利環境下では、定期預金の金利がインフレ率を下回ることが多く、実質的な資産価値が目減りしてしまうリスクが高まります。日本銀行は2%の物価上昇率を目標としていますが、定期預金の金利は多くの場合0.2%程度と大きく下回っている状況です。このような状況では、名目上は元本が保証されていても、実質的な購買力は低下していきます。
このインフレリスクに対応するには、定期預金だけに資産を集中させるのではなく、株式や不動産、REIT(不動産投資信託)など、インフレに強い資産にも分散投資することが重要です。これらの資産は、インフレ時に価格が上昇する傾向があり、定期預金では得られない実質的な資産価値の維持や成長が期待できます。
ただし、これらの投資にはリスクも伴うため、自分のリスク許容度や投資目的に合わせて、適切なバランスで資産を配分することが大切です。インフレリスクと投資リスクのバランスを考慮しながら、長期的な視点で資産形成を進めることが重要なポイントとなります。
資産運用としての限界
定期預金を資産運用の手段として考えた場合、いくつかの限界点があります。特に長期的な資産形成を目指す場合、定期預金だけでは十分な成果を得られない可能性があることを理解しておかなくてはなりません。
定期預金の最大の限界は、その低い運用効率にあります。2025年5月現在の日本の金融環境では、定期預金の金利は年0.2〜0.5%程度に設定されています。100万円を年利0.2%で10年間運用しても、税引前の利息はわずか約2万円に過ぎません。このような低金利では、将来に向けた資産形成は難しいと言わざるを得ません。
一方、他の投資商品に目を向けると、たとえば国内株式の長期平均リターンは年4〜5%程度、世界株式では年6〜7%程度とされています。もちろん、これらの投資商品にはリスクが伴い、元本割れの可能性もあります。ただし、過去のデータに基づく長期的な視点で見れば定期預金を大きく上回るリターンが期待できます。
具体的な比較例として、100万円を複利で20年間運用した場合のシミュレーションを見てみましょう。定期預金(年利0.2%)では約104万円、国内株式インデックスファンド(年利5%と仮定)では約265万円です。この差は運用期間が長くなるほど拡大し、資産形成における運用商品選択の重要性を示しています。
さらに、定期預金は流動性の制約もあります。満期前に資金が必要になった場合、中途解約すると金利が大幅に低下するというデメリットがあるため、資金の流動性を確保しつつ効率的に運用することが難しいという限界も。
このような定期預金の限界を踏まえると、長期的な資産形成においては、定期預金だけに頼るのではなく、株式や投資信託、REIT、外貨建て資産など、リスクとリターンのバランスを考慮しながら複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオ構築が重要となります。特に若いうちは、リスクを取れる期間が長いため、ある程度株式などのリスク資産に投資し、年齢とともにリスクを下げていくという長期的な戦略も考えられます。
定期預金の賢い運用方法

定期預金を効果的に活用するには、目的に合わせた預入期間の選択や、満期時の選択肢の理解、緊急予備資金としての活用方法、他の投資商品との組み合わせ方などを知ることが重要です。ここでは、定期預金の賢い運用方法について詳しく解説します。
定期預金は安全性が高い金融商品ですが、低金利環境では大きな収益は期待できません。そのため、単に預けるだけでなく、目的や期間に応じた戦略的な活用が求められます。また、他の金融商品と組み合わせることで、より効果的な資産形成が可能になります。
以下では、目的別の預入期間の選び方、満期時の選択肢と手続き、緊急の予備資金としての活用方法、投資信託などとの分散投資の組み合わせについて、具体的に見ていきましょう。
目的別の預入期間の選び方
定期預金を効果的に活用するためには、資金の目的に合わせて最適な預入期間を選択することが重要です。お金の使用目的や必要となる時期を明確にすることで、より計画的な資産形成が可能になります。以下の表に、目的別に最適な預入期間の選び方をまとめました。
| 資金の目的 | 特徴・注意点 | おすすめの預け方 |
| 結婚・出産資金 | • イベントまでの期間が明確 • 必要額が比較的予測しやすい | 結婚・出産予定日の2~3か月前を満期とする定期預金、または積立式定期預金で計画的に貯める |
| 住宅購入資金(頭金) | • まとまった資金が必要 • 住宅ローンとの組み合わせを考慮 | 3~5年の定期預金、または住宅購入時期に合わせた複数の定期預金を組み合わせる |
| 教育資金 | • 長期的な視点が必要 • 段階的な支出に備える | 入学時期に合わせた複数の定期預金を設定し、段階的に満期を迎えるようにする |
| 自動車購入資金 | • 比較的短期の目標 • 購入時期の調整が可能 | 購入予定の6か月~1年前を満期とする定期預金、または1~2年の積立式定期預金 |
| 老後資金 | • 長期的な資産形成が目的 • インフレリスクを考慮 | 定期預金と投資信託等を組み合わせ、定期預金は3~5年の複数に分散して預ける |
| 緊急予備資金 | • 急な出費に備える • 一定額を常に確保 | 一部は普通預金に、残りは3~6か月の短期定期預金を複数に分けて設定 |
| 旅行資金 | • 目標額が設定しやすい • 時期の調整が可能 | 旅行予定日の1~2か月前を満期とする短期定期預金、または積立式定期預金 |
預入期間を選ぶ際のポイントとしては、まず金融機関によって選択できる預入期間が異なることを理解しておくことが大切です。一般的には1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、5年などの選択肢が提供されていますが、全ての期間がどの金融機関でも利用できるわけではありません。
また、中途解約に備えて余裕を持った計画を立てることも重要です。予定より早くお金が必要になる可能性を考慮し、資金が必要な時期より少し前に満期が来るように設定するとよいでしょう。さらに、まとまった資金を一つの定期預金にまとめるのではなく、複数の定期預金に分散して預けることで、一部だけを引き出す柔軟性も確保できます。
目標金額が大きい場合は、ボーナス時に一括で預け入れる方法と、毎月少額ずつ積み立てる方法を組み合わせると効果的です。特に教育資金や老後資金など長期にわたる目標では、この組み合わせ方が便利です。
満期時の選択肢と手続き
定期預金が満期を迎えたとき、どのように資金を取り扱うかを事前に決めておくことも重要です。多くの金融機関では、満期時に選択できる3つの主要なオプションが用意されています。それぞれの特徴を理解して、自分の資金計画に合った選択をしましょう。
| 選択肢 | 概要 |
| 元利自動継続 | ・元金と利息を合わせた金額を、同じ期間の定期預金として自動的に継続する ・複利効果が期待できるため、長期的な資産形成に向いている ・ただし、継続時の金利は継続日の金利が適用されるため、金利低下局面では注意が必要 |
| 元金自動継続 | ・元金だけを同じ期間の定期預金として継続し、利息は普通預金口座に振り込まれる ・定期的に利息を生活資金として使いたい場合や、利息を別の用途に回したい場合に適している |
| 自動解約 | ・満期日に定期預金が自動的に解約され、元金と利息の合計額が普通預金口座に入金される ・満期後すぐに資金を使う予定がある場合や、別の金融商品への振り替えを検討している場合に便利 |
満期時の選択は、定期預金を申し込む際に指定することが一般的です。ただし、多くの金融機関では満期前に選択を変更することも可能です。変更手続きはインターネットバンキングやアプリで行える場合が多く、窓口やATMでも対応していることがあります。
元利自動継続を選択すると、資金が自動的に再投資されるため、満期を忘れていても資金が眠ることはありません。ただし、長期間取引がないまま自動継続を繰り返すと、「休眠預金」として扱われる可能性があるので注意が必要です。日本では、最終取引日から10年間取引がない預金は休眠預金となり、公益のために活用される仕組みになっています。
金利上昇が予想される局面では短期の預入期間を選んで元利自動継続にし、金利下降局面では長めの預入期間を選ぶといった戦略も効果的です。また、満期時には金融機関からのお知らせが届くことが多いので、その機会に改めて資金計画を見直すことも大切です。
緊急の予備資金としての活用
予期せぬ出費や緊急時に備えてお金を確保しておくことは、健全な資金管理の基本です。定期預金は、このような緊急予備資金(エマージェンシーファンド)としても有効に活用できます。
緊急予備資金として定期預金を活用する際には、「必要なときにすぐに引き出せる」という点と「無駄遣いを防ぐ」という点のバランスが重要です。普通預金はいつでも引き出せる反面、日常的に使いやすく、つい使ってしまう傾向があります。一方、定期預金は簡単には引き出せないため、緊急時以外に手を付けにくいというメリットがあります。
適切な預入額の設定方法としては、一般的には「3~6か月分の生活費」が目安とされています。具体的には、家賃・住宅ローン、食費、光熱費、通信費、保険料などの固定費と、最低限必要な変動費を合計した金額をベースに考えましょう。ただし、職業の安定性や家族構成、持病の有無などによって、必要な金額は異なります。不安定な収入の場合や、扶養家族が多い場合は、より多めの準備が望ましいでしょう。
また、緊急予備資金とは別に、家電の買い替えや自動車の修理など、予測可能な臨時出費に備えるための資金も定期預金で準備しておくと安心です。このような計画的な資金準備により、突発的な出費が発生しても、生活に大きな影響を与えることなく対応できるようになります。
投資信託等との分散投資との組み合わせ
定期預金は安全性が高い反面、低金利環境では大きな資産増加は期待できません。一方、投資信託などのリスク資産はより高いリターンが期待できますが、価格変動リスクがあります。これらを組み合わせることで、リスクとリターンのバランスがとれた効果的なポートフォリオ(資産の組み合わせ)を構築できます。
効果的なポートフォリオを作るための基本的な考え方は、「資産の目的と期間に応じた配分」です。短期的に必要となる資金や緊急予備資金は安全性の高い定期預金や普通預金に、長期的な資産形成を目指す資金はある程度リスクを取って投資信託などに配分するという方法が一般的です。
具体的な組み合わせ方としては、以下のような「時間軸による資産配分」が効果的とされます。
- 短期(1年以内に必要な資金):普通預金や短期の定期預金
- 中期(1~5年程度で必要な資金):定期預金や国債などの比較的安全な金融商品
- 長期(5年以上先の資金):投資信託や株式などのリスク資産
また、年齢によるリスク配分も重要な視点です。若いうちはリスク資産の比率を高め、年齢とともにリスク資産の比率を下げていくという「年齢から100を引いた数値を株式(リスク資産)の割合にする」という考え方があります。たとえば、30歳なら70%をリスク資産に、70歳なら30%をリスク資産に配分するという方法です。
リスク分散の観点から見た定期預金の役割は、ポートフォリオの「安定資産」としての機能です。市場が大きく下落したときでも定期預金の価値は変動しないため、ポートフォリオ全体の価値の変動を抑える効果があります。また、定期預金があることで、投資信託などが値下がりしたときでも焦って売却する必要がなく、長期的な視点で投資を続けられるというメンタル面でのメリットもあります。
さらに、「ドルコスト平均法」という投資手法と定期預金を組み合わせる方法もあります。毎月一定額を投資信託に積み立てながら、ボーナスなどのまとまった資金は定期預金に預け、市場が大きく下落したときに投資に回すという戦略です。これにより、相場の高い時期に大量購入するリスクを避けつつ、下落局面での投資機会を逃さないようにできます。
金利に左右されない資産運用が大切

定期預金は安全性が高く、計画的な資産形成に役立つ金融商品ですが長期的な資産形成を考えるうえでは、金利に左右されない運用方法も併せて検討することが重要です。
金利は経済状況や金融政策によって変動するため、定期預金だけに頼った資産運用では、金利の変動に大きく影響を受けてしまいます。
このような状況に対応するためには、定期預金のような「安定資産」と投資信託やETF(上場投資信託)などのような「リスク資産」を組み合わせた「分散投資」が効果的です。
特に近年は、スマートフォンを通じて手軽に資産運用できるサービスが充実しています。千葉銀行の「ちばぎんアプリ」もその一つです。アプリを通じて定期預金の作成ができるほか、投資信託の口座開設や購入、運用状況の確認まで行えます。
また、アプリ専用投資信託の購入時手数料は0円となっており、コスト面でも優れています。さらに、投信積立なら毎月1,000円以上1円単位から投資できるため、初めての方でも気軽に始められることができます。
定期預金による安定的な資産形成と、投資信託による成長性のある資産形成。両方をバランスよく組み合わせることで、金利環境に左右されにくく、かつ長期的に資産を増やしていける資産運用が可能になります。自分のライフプランやリスク許容度に合わせて、最適な資産配分を考えていきましょう。
金融環境は常に変化しています。単一の金融商品に依存するのではなく、複数の金融商品を活用し、リスクとリターンのバランスを取りながら資産形成を進めることが、将来の経済的なゆとりを生む土台となるでしょう。
「じっくり相談しながらご自身に合う資産運用を見つけたい。」
そんな方は、店頭窓口での専任担当者による、ご相談もいただけます。
土日祝日のご面談、平日夕刻のご面談にも対応する「コンサルティングプラザ」もご利用いただけます。
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
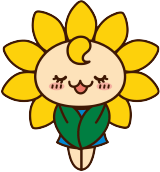
アンケートへのご協力
ありがとうございました。
当社は、お客様によりよいサービスを提供するため、cookie(クッキー)を使用することがありますが、これにより個人を特定できる情報の収集を行えるものではなく、お客様のプライバシーを侵害することはございません。